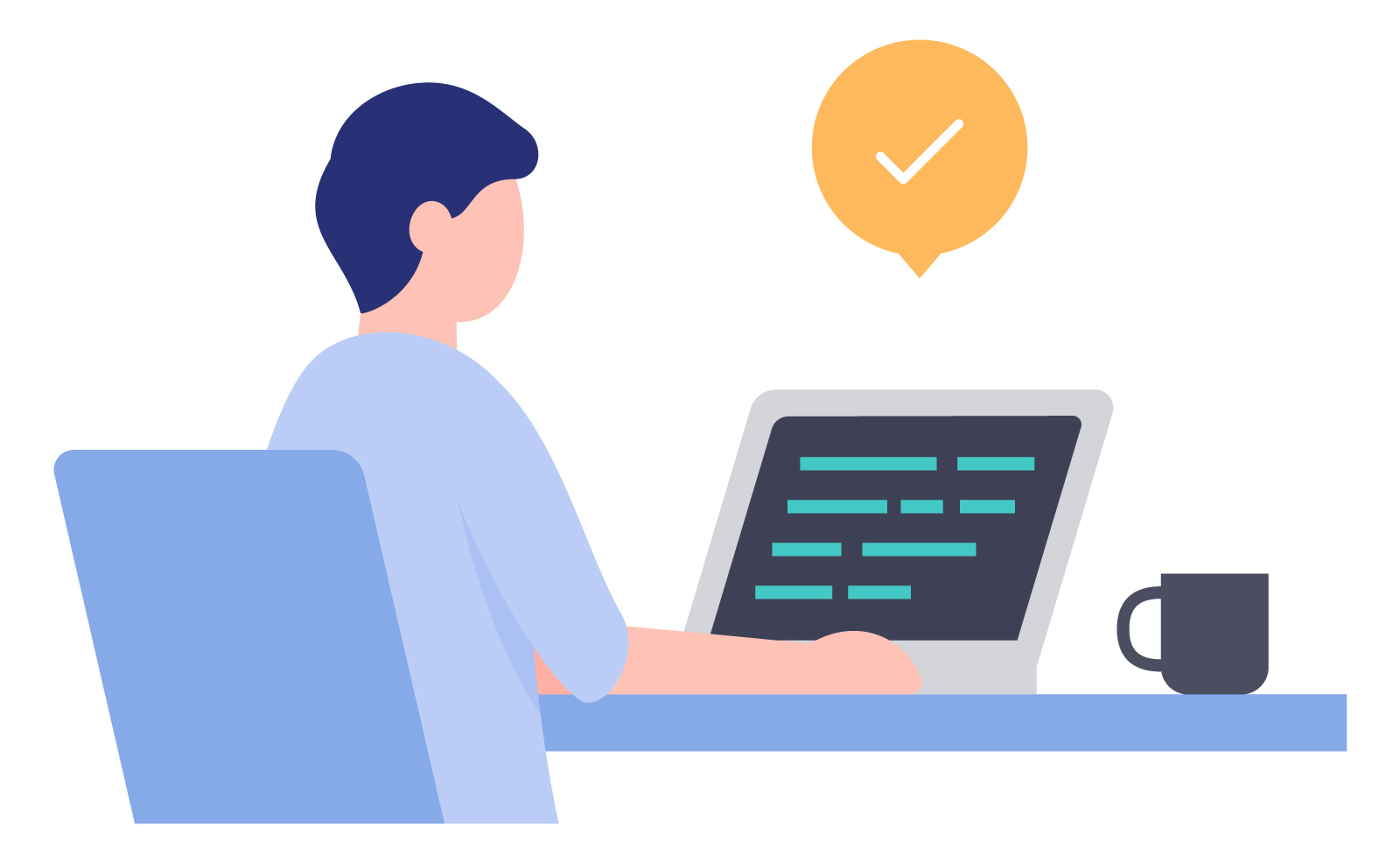セキュリティ運用を自動化するSOARのメリットと導入方法
サイバー攻撃の巧妙化やIT環境の複雑化により、企業のセキュリティ運用にはこれまで以上に迅速かつ的確な対応が求められています。しかし、アラートの増加や専門人材の不足といった課題から、現場では対応の遅れや属人化が深刻化しています。こうした状況を打開する手段として注目されているのが「SOAR(ソー)」です。
本記事では、SOARの基本から導入が求められる背景、期待される効果、導入時の注意点までをわかりやすく解説します。セキュリティ体制の強化や業務の標準化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
SOARとは
SOARとは、Security Orchestration, Automation and Responseの略で、セキュリティ運用における各種対応業務を自動化・効率化する統合基盤です。インシデントの検知から対応までの流れを一貫して管理し、手動作業の負荷を軽減するとともに、対応スピードの向上を支援します。
従来の環境では、アラートが発生するたびに複数のツールを横断して対応しなければならず、調査や判断に多くの時間が費やされてきました。SOARは、これらの運用プロセスを標準化し、ツール間の連携を自動で行うことで、属人的な判断やミスを減らす仕組みを提供します。
対応状況や作業履歴を記録・可視化できることから、セキュリティチーム内での情報共有や、組織全体としての改善活動にも活用可能です。近年はクラウドやリモート環境の拡大に伴い、組織をまたいだ広範な運用においても導入が進んでいます。
SOARが持つ主な機能
この仕組みが提供する代表的な機能は、大きく3つのカテゴリに分けられます。まずひとつ目は、各種セキュリティツールをつなげ、業務フローを自動化する“オーケストレーション”機能です。これにより、複数のシステム間の手動操作を省略し、作業効率が大きく向上します。
二つ目は、分析や報告に関わる処理の自動実行です。アラート発生時に定型的な調査を自動で行い、対応の必要性や優先度を判別する仕組みを構築することで、現場の負担を大幅に軽減します。定められたルールに従って、通知、隔離、ブロックなどの初期対応を即座に行える点も特徴です。
三つ目は、記録と可視化です。対応の全体像をログとして蓄積し、時系列で振り返ることが可能です。これにより、再発防止策の検討や改善活動のベースとしても活用できます。
これらの機能は単独で使うのではなく、組織内の運用ルールや対応プロセスと組み合わせることで、より実践的な効果を発揮します。結果として、人的リソースに依存しない、安定的かつ迅速な体制の構築が可能になります。
SOARが注目されている3つの理由
情報セキュリティの現場では、日々大量のアラートやインシデント対応に追われ、担当者の負担が増大しています。加えて、サイバー攻撃の巧妙化により、即時対応が求められるケースも増加中です。こうした背景のもと、限られた人員でも迅速かつ正確な対応を実現する手段として、SOARの導入が注目を集めています。
セキュリティ運用の人的負荷と応答時間の課題
企業や組織が扱うデータやシステムが拡大するなか、セキュリティ対策も複雑化しています。セキュリティ運用チームは、監視・分析・対応といった一連の業務を日々繰り返していますが、対応すべきアラートやログの量は膨大で、すべてを人手で処理するには限界があります。
特に課題となるのが、アラートに対する「対応の遅れ」です。検知から調査、判断、対処までに時間がかかれば、攻撃の被害を拡大させるリスクが高まります。また、同様の手順を繰り返す業務はミスや見落としが発生しやすく、属人化による対応品質のばらつきも避けられません。
さらに、セキュリティ人材の確保が難しいという現実も大きな壁です。限られた人員で多くの対応を担わなければならない状況では、精神的な負担やオーバーワークも深刻になりがちです。こうした状態を放置すれば、対応の精度やスピードが低下し、重大インシデントへの対応力も損なわれかねません。
このように、セキュリティ運用の現場では人的リソースの限界と時間との戦いが常態化しており、そこを補完・強化する仕組みとしてSOARへの期待が高まっています。
アラート過多・誤検知による対応の非効率性
セキュリティ運用における大きな課題のひとつが、膨大なアラートへの対応です。監視システムやセンサーが高度化したことで検知精度は向上していますが、それと同時に通知過多の状況も生まれています。中には実害のないものや、既知の挙動による誤検知も含まれており、それらを手作業で仕分けるには大きな労力がかかります。
このノイズの多さは、対応スピードと的確性の低下を引き起こします。たとえば、重大なインシデントと判明するまでに多数の無関係なアラートに時間を取られてしまえば、対応の初動が遅れ、被害の拡大を招く可能性があります。特に誤検知が頻発すると、運用担当者が“アラート疲れ”に陥り、見落としや判断ミスを誘発するリスクも否めません。
SOARを活用することで、定型化されたアラート処理や調査フローを自動化し、対応が必要なものだけを選別する体制を構築できます。これにより、セキュリティチームが本来注力すべき重要インシデントへの対応に集中できるようになります。情報の精査と優先順位づけを自動で行えることが、運用の質と効率を同時に高めるポイントとなります。
インフラ・クラウド環境の複雑化
企業のIT環境は、従来のオンプレミス中心の構成から、クラウドやSaaSの活用を含むハイブリッド型へと大きくシフトしています。業務システムやストレージが社内外に分散し、ネットワーク構成も複雑化するなかで、従来の監視・対応体制では全体を把握しきれないケースが増えています。
このような環境下では、セキュリティ監視の対象も多岐にわたり、ログやアラートが複数の拠点やクラウドベンダーにまたがることが一般的です。結果として、情報の収集や相関分析に多大な時間とスキルが必要となり、即応性が損なわれるリスクが高まります。また、サービスごとに監視ツールや運用ルールが異なることで、対応にばらつきが生じる要因にもなります。
SOARは、こうした複雑な構成環境においても、異なるシステムやクラウドサービスと連携し、統一されたワークフローの中でインシデント対応を管理できる点が強みです。複数のデータソースを自動で取り込み、関連づけて判断する機能を活用すれば、状況の全体像を迅速に把握することが可能になります。
インフラが多様化する中で、対応の統制力と可視性を保つ仕組みとして、SOARの活用価値は今後さらに高まると考えられます。
SOAR導入のメリットと導入効果
セキュリティ運用における効率化と精度の両立は、多くの組織にとって課題となっています。SOARは、単なるツールの自動化ではなく、業務全体の標準化と迅速化を可能にするプラットフォームです。ここでは、SOARを導入することで得られる代表的な効果を、実際の運用観点から具体的に解説します。
対応速度の向上と調査時間の短縮
セキュリティインシデントに対して迅速な対応が求められるなか、初動の遅れは被害拡大や業務停止といった深刻な影響を及ぼす可能性があります。従来の運用では、ログの確認や関係システムの調査、関係者への連絡といった手順をすべて人手で行っていたことから、対応にかかる時間が長くなりがちでした。
SOARを活用すれば、こうした初期対応の多くを自動化することが可能になります。たとえば、アラートが発生した時点で、事前に定義されたプレイブックに基づき、自動で該当ログの収集・分析、関連情報の突合、チケットの発行といった一連の流れが処理されます。これにより、担当者が実際に判断・対応を行う前に、必要な情報がすでに揃った状態になることで、初動が格段に早くなります。
過去の対応履歴や類似インシデントのパターンをもとに、最適な対応フローを選択することもでき、判断の精度も向上します。人が介在するタイミングを絞り込み、分析作業を最小限に抑えることで、リソースを本来注力すべき業務に集中させることができます。
操作の標準化とミス防止
セキュリティ運用では、同じような対応を繰り返し実施する場面が多く存在します。しかし、現場の判断や担当者のスキルに任せた対応では、処理のばらつきや記録漏れが発生しやすく、組織全体の運用品質にムラが出てしまうことがあります。特に、複数の担当者が交代で対応している場合は、手順の引き継ぎ不足が重大なミスにつながることもあります。
SOARの導入によって、こうした課題は大きく緩和されます。あらかじめ定義された「プレイブック」に従って各対応が自動的に実行されることにより、誰が対応しても同じ品質が保たれるという安心感があります。手順ごとにチェックポイントが明確に設計されており、作業の漏れや誤操作を防ぐ設計が施されている点も大きな特徴です。
また、対応のプロセスが明文化・可視化されることで、新任の担当者でもスムーズに運用に加わることが可能になります。経験値に依存しない仕組みを構築できることで、属人化の解消にもつながります。
業務を標準化し、再現性の高い対応を可能にすることは、インシデント対応の信頼性を高めるだけでなく、全体としてのセキュリティレベルを底上げすることにもつながります。
コスト削減・ROIの改善
セキュリティ対策と聞くと、「コストがかかるもの」という印象を持つ方も少なくありません。たしかに、SOARの導入には初期投資が必要ですが、中長期的に見ると運用コストの削減と投資対効果の向上という大きなメリットが期待できます。
まず、人手による対応を自動化することで、対応にかかる工数を大幅に削減できます。1件ごとに数時間を要していたインシデント対応が、定型業務の自動化によって短時間で完了するようになれば、担当者の負荷は軽減され、同時に人件費の圧縮にもつながります。
ミスや見落としによる損失リスクを抑えられる点も、間接的なコスト削減効果として見逃せません。対応の精度が上がることで、被害の拡大や後処理にかかるコストを未然に防ぐことができます。
さらに、迅速な対応と記録の一元化により、監査対応や社内報告にかかる手間も最小限に抑えられます。これにより、セキュリティ部門だけでなく、全社的な業務効率の向上にも寄与します。
導入のハードルと注意点
SOARは高い効果を期待できる一方で、導入にはいくつかの注意点も存在します。自動化や標準化が進むことで利便性は向上しますが、運用環境や体制に合わない導入を行うと、かえって混乱を招くこともあります。ここでは、導入時によくある落とし穴や、実装後に起こりやすい課題について整理し、失敗を防ぐ対策を紹介します。
過度な自動化のリスク
多くのプロセスを自動化できる点が魅力ですが、その強力さゆえにやりすぎによるリスクも生じます。すべてを自動で処理することを優先しすぎると、人の判断が必要な場面まで自動化してしまい、誤対応や対応漏れにつながる可能性があります。
たとえば、誤検知されたアラートに対して自動的に端末を隔離したり、通信を遮断したりすると、業務に支障をきたす事態になりかねません。また、ルールが不十分なまま運用を開始すると、現場の意図とは異なる挙動をシステムが取ってしまう恐れもあります。
さらに、自動化のブラックボックス化も注意が必要です。自動処理の内容を現場担当者が十分に理解していないと、トラブル発生時の原因特定や対応が遅れ、被害が拡大することもあります。
SOARの効果を最大限に引き出すには、すべてを自動に任せるのではなく、「どこまでを自動化し、どこからを人が判断するか」という境界を明確に設計することが重要です。プレイブック作成時には、条件分岐や確認プロセスを適切に挟み込み、必要に応じて人の介在を促すフローを設計することが、安定した運用につながります。
システム統合・データ連携の困難さ
多くの組織が直面するのが、既存システムとの統合やさまざまなセキュリティツールとのデータ連携の難しさです。SOARは単体で完結する仕組みではなく、EDR、SIEM、ファイアウォール、脅威インテリジェンスなど、複数の情報源と連携することで初めて本来の機能を発揮します。
しかし、現場では製品ごとにAPI仕様が異なっていたり、必要なログ形式が標準化されていなかったりと、技術的なギャップが障壁となるケースが少なくありません。特に、クラウドとオンプレミスをまたぐ環境では、情報の一元管理が難しく、処理の整合性を確保するには高度な設計と設定が必要です。
さらに、外部システムとの通信やデータの出力・加工処理をどこまで自動化できるかも導入のハードルになります。実際には、連携先ごとに個別の調整やカスタマイズが求められることが多く、導入コストや構築期間が膨らむ要因となっています。
こうした背景から、導入前にはどのシステムとどのように連携させるのかを明確にし、それぞれの技術要件と可用性を洗い出しておく必要があります。あらかじめ統合範囲を見極めることで、スムーズな運用開始と安定した稼働につながります。
ツール選定と運用体制の整備の重要性
新しいツールを導入する際には、どう運用するかを見据えた全体設計が不可欠です。なかでも重要なのが、自社の業務特性や体制に合ったツールを選ぶこと、そして導入後の運用体制を整えることです。
市場には多種多様なSOAR製品が存在しており、機能の幅や連携性、拡張性、UIの使いやすさなどに差があります。どれだけ多機能であっても、現場の課題と合致していなければ使いこなすことができず、結果として定着しない恐れがあります。
また、ツールの導入と並行して運用ルールや体制を構築していくことも欠かせません。プレイブックの設計、対応ポリシーの明文化、関係部門との連携フローなど、人的な側面も含めた整備が求められます。担当者が交代しても運用を継続できるように、ドキュメント化と教育体制の整備も不可欠です。
導入後は運用して終わりではなく、定期的な見直しや改善サイクルの運用も重要です。アラートの傾向や業務フローの変化に応じてプレイブックを調整し、常に最適な状態を維持することが、最大限の効果を引き出す鍵となります。
まとめ
SOARは、セキュリティ運用の効率化と迅速化を実現する次世代のプラットフォームとして、注目を集めています。人手に頼らざるを得なかったインシデント対応や調査業務を自動化し、属人化やミスを防ぐことで、組織全体のセキュリティレベルを底上げすることが可能です。
一方で、導入にはシステム間の連携設計や、プレイブックの整備、適切なツール選定といった準備が不可欠です。また、自動化の境界を明確にしないまま運用を開始すると、逆にリスクを招く可能性もあります。
SOARはあくまで運用体制を支える仕組みであり、それを効果的に活かすには、組織の課題や体制に合った設計と継続的な改善が求められます。自社にとって本当に必要な機能を見極め、段階的に取り入れることが成功への第一歩です。