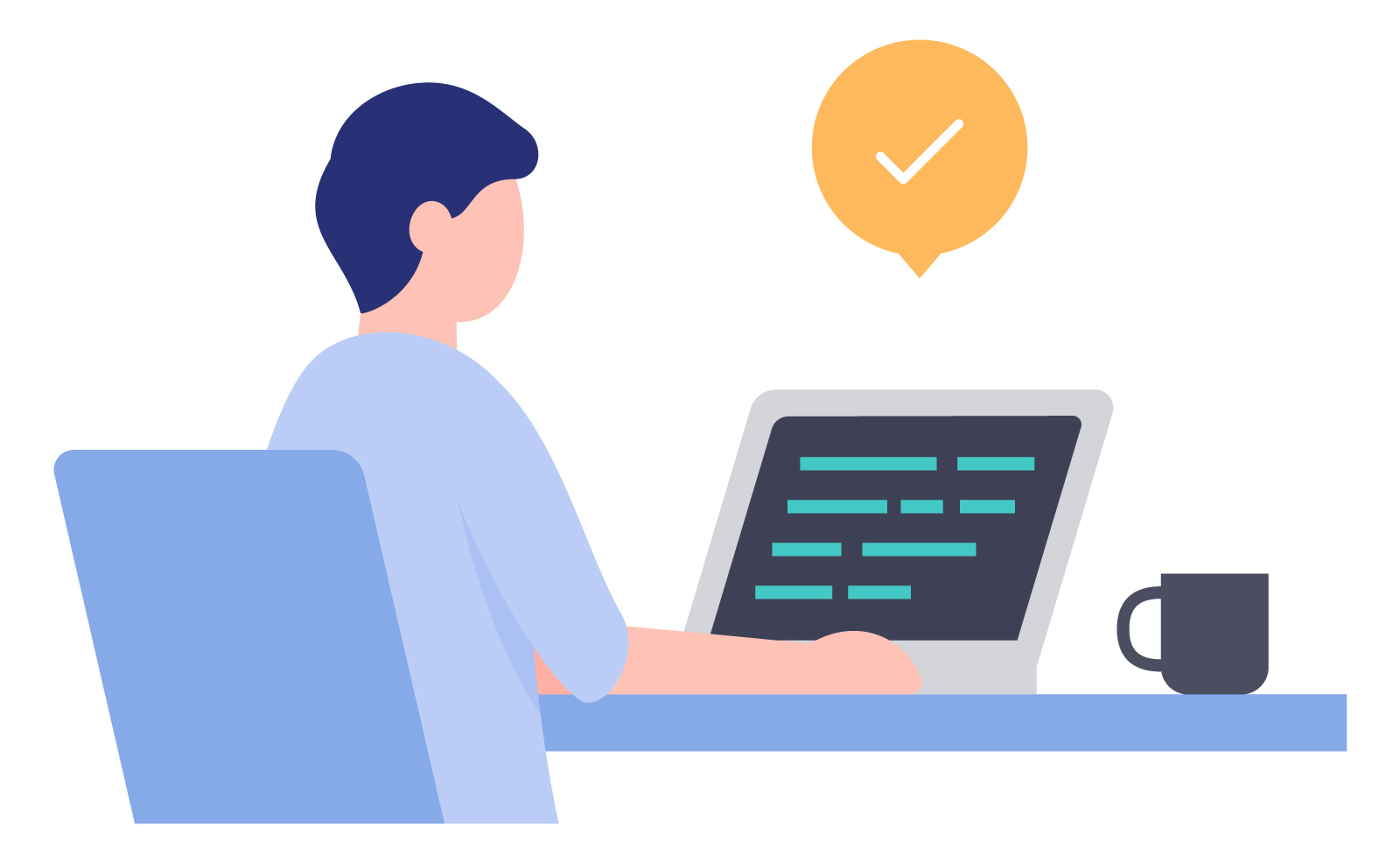UTMで情報システムを一括管理!導入のメリットを紹介
企業の情報システムを守る方法は多様化していますが、複雑になるほど管理の手間も増え、担当者の負担は大きくなります。特に拠点が複数に分かれている企業では、拠点ごとに異なる対策が行われることで統一性を欠き、思わぬ抜け穴が生じる危険があります。
こうした状況を解決する手段として注目されているのがUTM(統合脅威管理)です。複数の防御機能をひとつの仕組みに集約し、一元的に監視や運用を行えるのが特徴です。
本記事ではUTMの基本から導入メリット、オンプレ型とクラウド型の違い、導入前に確認すべきポイントまでを整理し、企業が効率的に対策を進める際のヒントを紹介します。
UTM(統合脅威管理)とは?
統合型の仕組みは、複数の防御機能をひとつにまとめて扱う考え方です。従来はファイアウォールやウイルス対策、侵入検知といった仕組みを個別に導入し、別々に運用するのが一般的でした。しかしその方法では、設定や監視が複雑化し、担当者の負担が増えるうえ、管理の抜けや重複が起こりやすいという課題があります。
統合型のアプローチでは、こうした複数の仕組みを一か所に集約することで、一貫したルールで制御できるのが特徴です。
UTMに搭載される主な機能
統合型の仕組みには、多様な防御機能が組み込まれています。代表的なものを以下に整理しました。
| 機能 | 役割・目的 |
|---|---|
| 外部通信の制御 | 不正なアクセスを遮断し、内部ネットワークを守る |
| ウイルス検知 | 既知のマルウェアや不審ファイルを検出・排除 |
| 侵入検知・防御(IDS/IPS) | 通信内容を監視し、怪しい挙動を発見・遮断 |
| Webアクセス制御 | 危険サイトや業務に不要なページへの接続を制限 |
| 迷惑メール対策 | スパムやフィッシングをブロックして被害を抑止 |
| アプリケーション制御 | 不要または危険なアプリの利用を制限 |
| リモート接続保護 | 外部からの接続を安全に管理 |
| サンドボックス機能 | 未知の脅威を仮想環境で検証し侵入を阻止 |
従来はこれらの機能をそれぞれ別製品で運用していましたが、統合することで一貫性が生まれ、設定や監視の手間を大幅に削減できます。
また、ひとつの仕組みの中で全体を把握できることで、担当者が複数の画面を行き来する必要がなくなり、効率的に全社的な対策を進められます。こうした効率性と網羅性が、統合型アプローチの大きな強みといえるでしょう。
UTMの導入で得られるメリットと注意点
複数の機能を一括管理できる仕組みを導入することは、効率化やコスト削減だけでなく、企業全体での統一的なルール運用を可能にします。一方で性能面や運用体制に関する課題もあり、利点と注意点を正しく理解することが重要です。
多拠点でも統一した対策が可能になる
拠点が分散している企業では、場所ごとに異なる機器やルールが導入されているケースが少なくありません。支店や営業所ごとに担当者の知識や経験が異なれば、設定や運用にばらつきが生じ、結果として本部が把握できない見えないリスクが残ることになります。統合型の仕組みを活用すれば、すべての拠点に同じルールを適用し、一括で制御することが可能です。これにより、各拠点の環境差に左右されずに、統一的な基準で防御を実現できます。
可視性の向上もメリットのひとつです。本部から各拠点の通信状況や不審な挙動を把握でき、異常が起きた場合も迅速に対応可能です。拠点が国内外に広がる企業にとっても、遠隔で状態を確認し、必要に応じて設定変更を即時に反映できることは大きな魅力です。
このように、分散した組織全体を統一したポリシーで守れる点は、複数拠点を抱える法人にとって導入効果の大きな柱となります。
運用負担を軽減できる一方で性能面に課題も
UTMを導入すると、複数の防御機能を一元的に管理でき、運用担当者の手間が大幅に減ります。これまではファイアウォール、アンチウイルス、侵入防御などを個別に操作していたものが、一つの管理画面で完結するようになり、設定の統一やログの集約が容易になります。その結果、属人化を防ぎ、組織全体で効率的な運用が可能になります。
ただし注意すべきは、複数の機能を一台にまとめることで処理が集中する点です。アクセス数や通信量が多い拠点では、同時に大量のデータを処理する必要があり、装置の性能が追いつかない場合があります。その結果、通信速度の低下や業務システムの遅延といった問題につながることがあります。
さらに、すべての防御機能を同じ仕組みに依存することで、万が一障害が発生した際には全体の防御力が低下するリスクも考慮しなければなりません。導入の際には必要な処理能力を見積もり、将来的な拠点や利用者の増加を踏まえて余裕を持った選定を行うことが求められます。
コストと人材リソースをどう確保するかがポイント
統合的な対策を導入することは、長期的にはコスト削減につながりますが、初期費用や運用体制の整備には一定の投資が必要です。装置そのものの導入費用に加え、保守契約やアップデートの費用も継続的に発生します。特に多拠点展開をしている企業では、全体規模に合わせた導入が必要となることから、費用が膨らみやすい点は無視できません。
また、運用を担う人材リソースの確保も大きな課題です。仕組みが統合されていても、ポリシー設定やログの分析、異常検知への対応などは専門知識を持つ担当者の関与が不可欠です。しかし、中小規模の企業では専門部署を設けられない場合も多く、外部ベンダーやマネージドサービスに依存するケースも少なくありません。
したがって、導入を検討する際には単純に機能や価格だけを見るのではなく、自社にどの程度の運用体制があるのかを見極めることが重要です。必要に応じてアウトソーシングを組み合わせることで、限られた人材リソースでも効果的な運用を継続できる体制を構築することができます。
オンプレ型とクラウド型の違い
統合的な仕組みには、機器を自社に設置して利用する方法と、サービスとして外部提供を受ける方法があります。どちらを選ぶかは、利用環境や拠点の状況によって適性が異なります。ここでは両者の特徴を整理し、適したシーンを考えます。
それぞれの特徴と適したシーン
オンプレ型は、専用の装置を社内ネットワークに設置して利用する方式です。自社で管理することから細かな設定変更が可能で、通信経路も社内で完結し、速度や安定性を確保しやすい点が特徴です。特に金融機関や医療機関など、高度なセキュリティ要件や厳格な運用ルールが求められる環境では適しています。一方で、導入や保守にかかる初期費用や人的リソースが大きく、拠点ごとに設置する場合はコストが膨らみやすいという課題があります。
クラウド型は、インターネット経由でサービスを利用する仕組みで、専用機器を設置する必要がありません。拠点数が多い企業でも一括で管理でき、遠隔地の拠点やリモートワーク環境でも導入しやすいのが利点です。システム更新や脅威情報のアップデートも自動で行われることで、担当者の負担を軽減できます。ただし、通信がインターネット経由になることから、回線状況によっては遅延が発生する可能性があり、大容量データを扱う業務では注意が必要です。
このように、安定性や高度な制御を重視する場合はオンプレ型、拠点数の多さや運用負荷の軽減を優先する場合はクラウド型が適しているといえるでしょう。
通信速度や帯域に与える影響
UTMを利用する場合、複数の防御機能が通信を逐一チェックすることで、処理負荷が高くなります。その結果、トラフィックが集中する時間帯には速度低下を招く可能性があります。特にオンプレ型の場合、導入時に装置の処理能力を過小に見積もると、業務アプリケーションやクラウドサービスの利用に支障をきたす恐れがあります。
クラウド型も同様に、インターネット経由での利用となることから回線の品質が重要です。国内外に拠点を持つ企業では、地理的条件や回線契約の違いにより、応答速度が拠点ごとに異なるケースもあります。帯域を圧迫する大容量データの転送や映像通信を多用する環境では、回線増強や分散処理の検討が欠かせません。
対策としては、導入前に実際の通信量を把握し、ピーク時を想定した余裕のある処理能力を確保することが重要です。また、必要に応じて一部機能を分散運用したり、回線を冗長化するなど、性能劣化を防ぐ仕組みを設けることが望まれます。
サポート体制や拡張性の比較
導入形態を選ぶ際には、提供されるサポート体制や将来的な拡張性も重要な判断材料になります。オンプレ型の場合、自社に機器を設置することから自由度は高いものの、障害対応やアップデートは自社で行う必要があります。専門知識を持つ人材がいれば柔軟に運用できますが、逆に人材不足の企業では負担が重くなりがちです。
一方、クラウド型ではサービス提供者が更新や脆弱性対応を行うことで、常に最新の状態を維持できます。障害発生時にもベンダーが対応する仕組みが整っていることが多く、専門要員を抱えにくい中小規模の企業には適しています。ただし、サービス範囲外の個別要望には対応できない場合もあり、柔軟性ではオンプレ型に劣る部分があります。
拡張性の観点では、拠点が増えるたびに機器を追加しなければならないオンプレ型よりも、利用規模に応じて契約を変更できるクラウド型が有利です。ただし、通信量や利用者数の急増に備え、サービス側のスケーラビリティやサポート体制が十分かどうかを確認することが欠かせません。
UTMを導入する前に確認すべきポイント
新しい仕組みを導入する際には、機能や価格だけで判断するのではなく、自社の環境や運用体制を踏まえて準備を進めることが欠かせません。ここでは、事前に確認しておくべき要素を整理し、失敗を防ぐ方法を解説します。
現状のネットワーク環境を棚卸しする
導入前の準備としてまず行うべきは、自社ネットワークの現状把握です。どの拠点にどのような機器が配置されているのか、回線速度や契約内容、利用しているクラウドサービスの種類などを正確に洗い出す必要があります。こうした棚卸が不十分なまま新しい仕組みを導入すると、既存システムとの相性が合わず、想定外のトラブルが発生する恐れがあります。
特に、多拠点展開をしている企業では、拠点ごとに回線品質や利用環境が異なります。ある拠点では高速な光回線を利用していても、別の拠点では低速回線やモバイル通信に依存していることもあり、同じ条件で運用するのが難しいケースもあります。これらを考慮せずに統一的な仕組みを導入すれば、一部拠点で速度低下や業務への支障が出る可能性があります。
また、既存のファイアウォールやルーターなどとの役割分担をどうするかも重要な検討点です。棚卸によって現状を整理すれば、不要な機器を統合でき、投資効率を高めることにもつながります。事前の調査を丁寧に行うことが、導入後のスムーズな運用に直結するのです。
ポリシー設定や運用ルールの整合性
統合的な仕組みを導入しても、拠点ごとに運用ルールが異なれば効果は半減します。たとえば、本部では厳格なアクセス制御を行っていても、支店では緩やかな基準が適用されていると、全体の安全性に穴が生じます。ポリシーを設定する際には、企業全体で共通の基準を設けると同時に、現場の業務に支障をきたさない柔軟性も必要です。
また、業務内容や組織の性質によって最適なルールは異なることから、画一的な設定だけでは不十分です。営業拠点では外部との通信が多く必要になる一方で、研究部門では外部接続を最小限に抑えるといった調整が求められます。これらを本部と現場で調整し、整合性のある方針として明文化することが大切です。
さらに、運用ルールは一度作ったら終わりではなく、定期的に見直しを行うべきです。新しい業務システムの導入や外部環境の変化に応じて更新を怠ると、ルールが実態に合わなくなり、抜け穴を生む要因となります。ポリシーの一貫性と柔軟性を両立させることが、安定した運用につながります。
ログ監視やアラート体制の整備
導入した仕組みを有効に活用するには、日々のログ監視とアラート運用が欠かせません。外部からの不審な通信や内部での異常な挙動は、まずログに現れます。これを把握せず放置すると、攻撃が長期間潜伏し被害が拡大する危険があります。
しかし、ログは膨大な量となることから、人手で逐一確認するのは現実的ではありません。アラートを活用し、重大度の高い事象を優先的に通知する仕組みを整えることが重要です。例えば、管理者にメールやダッシュボードでリアルタイムに知らせる体制を構築すれば、初動対応の迅速化が可能となります。
また、アラートの閾値設定が適切でないと、重要な警告を見逃したり、逆に不要な通知が多発して担当者が疲弊したりすることもあります。したがって、実際の運用を通じて設定を調整し、精度を高めていく必要があります。さらに、万一の障害やインシデント発生時に備え、通知先や対応フローを明確にしておくことで、被害を最小限に抑えられます。
まとめ
複数の防御機能を一元的に扱える仕組みは、運用効率を高めながら全体のリスクを低減する有効な方法です。特に多拠点を展開する企業にとって、拠点ごとのルールや機器に依存せず、統一された基準で管理できる点は大きな利点といえます。
一方で、性能やコスト、人材リソースといった課題も存在することから、導入前の棚卸や運用ルールの策定、アラート体制の整備など準備が欠かせません。オンプレ型とクラウド型にはそれぞれ特性があり、自社の規模や業務特性に応じて最適な形を選ぶことが重要です。