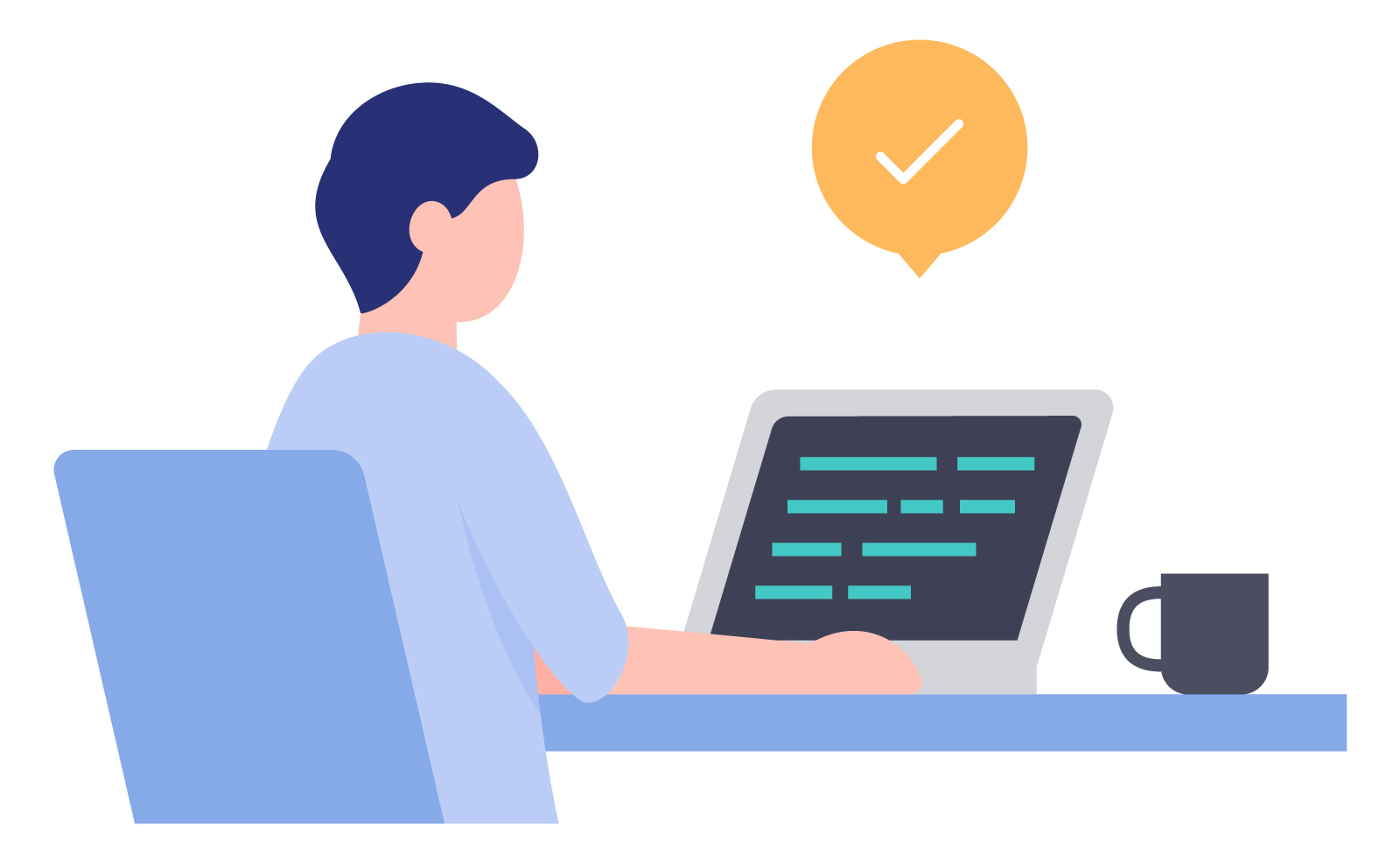ゼロトラストとは?従来との違いや導入のメリットを解説
近年、社内であればセキュリティリスクは低く安全、という境界型の考え方では、クラウド活用やテレワークが広がる現代の業務環境には対応しきれなくなっています。
特に本社・支社・工場など拠点が分散している企業においては、拠点間の通信経路や従業員のITリテラシーの差がセキュリティの大きな穴となりかねません。ゼロトラストは、こうした分散型企業の課題を解決する有効な手段として注目を集めています。
本記事では、ゼロトラストの基本的な仕組みや境界型との違い、導入によるメリットと注意点、そして実際に導入する際に必要な要素について、わかりやすく解説します。
ゼロトラストとは?

多様な働き方やクラウドサービスの活用が進むなか、社内と社外の区別だけでは情報を守りきれない時代に突入しています。こうした変化に対応する新たな対策として注目されているのが、「信頼を前提にしない」モデルです。
この考え方では、ユーザーや端末、通信内容に対して常に正当性の確認を行い、必要に応じて制限を加えることで被害の拡大を防ぎます。あらゆる経路を対象とし、業務に支障が出ない範囲でアクセスを最適にコントロールすることを目指しています。
特に拠点が分散している企業では、各拠点ごとの対策レベルやネットワーク構成に差が出やすく、全社的に一貫した仕組みを構築するうえで有効とされています。このモデルは単なる仕組みの切り替えではなく、日々の業務や管理体制そのものを見直す契機ともなるでしょう。
ゼロトラストモデルの基本原則
このモデルの核となるのは、「信頼せず、必ず検証する」という思想です。組織内であっても、アクセス元や接続された機器、通信の内容について逐一確認を行い、一定の基準を満たしたものだけに許可を与える設計となっています。
一度許可された接続であっても、その後の動きが疑わしければ即座に制限されることもあります。これは単にログイン時の認証にとどまらず、通信の暗号化や行動の分析、端末の状態チェックなど複数の要素を組み合わせることで実現されています。
またこのモデルでは、最小権限の原則が重視されます。利用者には、その業務に必要な範囲のみの操作権限を与え、それ以外の情報や操作にはアクセスできないようにします。これにより、万が一内部から不正が行われた場合でも、影響を局所に抑えることができます。
こうした仕組みの積み重ねにより、単一の境界ではなく、多層的な検証と制御による防御が成立するのです。
境界型セキュリティとの違いは?
かつては、「内と外」を明確に分けることで情報を守る手法が一般的でした。いわゆる境界型と呼ばれるこの考え方では、社内ネットワークに一度入ってしまえば、比較的自由に業務を進められる構造になっています。この仕組みは、オンプレミスを前提とした時代には有効でしたが、クラウドサービスの活用やモバイル端末の普及が進むにつれ、境界そのものが曖昧になってきました。
一方、近年採用されるようになった新しい方式では、信頼の前提を排除し、すべての通信や操作を検証対象とします。たとえ社内からのアクセスであっても、ユーザーや機器の正当性、利用状況を逐一チェックし、問題があれば即座に遮断する仕組みが基本です。
このように、特定のネットワークを安全圏と見なすのではなく、常に警戒と確認を続けることで、より実態に即したリスク対策が可能になります。働き方の多様化が進む中で、この柔軟で堅牢な考え方が注目を集めています。
ゼロトラストが重視する3つのポイント
このモデルの実装において重要となるのが、以下の3点です。
- 継続的な認証
- 最小限の権限設定
- 可視化と監査
まず、継続的な認証とは、ログイン時の確認だけでなく、業務中の挙動や接続状況を常時モニタリングし、異常があれば即時に制御を加える仕組みです。これにより、なりすましや乗っ取りといった脅威を早期に検出できます。
次に、最小権限の考え方では、業務に必要な機能や情報だけにアクセスを許可します。過剰な権限を持たせないことで、仮に内部の利用者が悪意を持って行動した場合や、情報が外部に流出した場合でも、被害を最小限に抑えることができます。
最後に、可視化と監査の体制を整えることも欠かせません。ユーザーの行動履歴やアクセス先の記録を残し、後からの検証や調査ができるようにしておくことで、再発防止や法的対応にも備えられます。これらの要素が連動することで、柔軟かつ堅実な運用が可能となります。
ゼロトラストを導入するメリット

すべてのアクセスを前提なく見直すという発想は、従来の対策とは異なる安心感をもたらします。業務が多様化するなかで、この考え方には複数の利点が存在し、単なる防御強化にとどまらない価値を生み出します。ここでは、企業の実務において実感されやすい効果に絞って解説していきます。
社内・外を問わず高度なアクセス制御が可能
従来のネットワーク運用では、社内からの接続は信頼され、外部からの接続は疑われるという構造が一般的でした。しかし、クラウド活用が進み、オフィスの内外で同じ業務が行われるようになった今、この境界はほとんど意味を持たなくなっています。
そこで必要になるのが、場所や端末の種類を問わず、一貫した制御が行える仕組みです。この仕組みでは、アクセス元の信頼性を接続のたびに検証し、利用状況を常に確認しながら適切な権限を割り当てます。これにより、社内ネットワークに潜んでいた脆弱なポイントや、テレワーク時の隙間をカバーすることが可能になります。
また、多段階認証や端末の状態チェックといった仕組みを組み合わせることで、より精度の高い管理が行えるようになります。IT部門は、拠点の場所に関係なく、すべての接続を一元的に見渡せるようになり、全体の透明性と統制力が高まります。
拠点間・クラウド間通信のセキュリティが強化される
拠点を複数展開している企業では、社内ネットワークの整備状況や機器の更新頻度が場所ごとに異なることが少なくありません。各拠点をつなぐ通信経路やクラウド上のデータ連携が、思わぬリスク要因になるケースもあります。
新しいアプローチでは、拠点やクラウドに接続する経路そのものを信頼せず、常に暗号化や認証を通じた制御を前提とすることから、不均一な状況下でも安定した運用が可能です。ネットワークの境界に頼らずに、閉域網とインターネットを併用していても安全性を確保できます。
さらに、重要な業務システムをクラウドに置いた場合でも、その通信が誰によって、どこから、どの端末で行われているのかを把握しながら制御できます。これにより、本部と支店、または本社と外部委託先との間でやり取りされる情報が、安全に保たれる環境が整います。
内部からの脅威に強い
情報漏洩や不正アクセスと聞くと、外部からの攻撃を想像しがちですが、実際には内部の関係者による事故や意図的な行為が深刻な被害を生むケースも少なくありません。たとえば、退職予定の社員によるデータ持ち出しや、権限が過剰なアカウントの悪用などが挙げられます。
こうした状況において、すべての操作に対して記録を残し、権限を必要最低限に限定する設計は非常に有効です。特に、アクセスのたびに確認を行う仕組みは、常に状態を監視し続けるという点で、信頼だけに依存しない運用を可能にします。
また、業務範囲に応じて細かくアクセスを制限することにより、不用意な情報閲覧や誤操作も抑止できます。問題が起きた際にも、いつ・誰が・どのデバイスから操作したのかを可視化でき、早期対応と再発防止に直結します。
目に見えない内部のリスクに対して、事前に防壁を築くことができる点は、大きな安心材料のひとつです。
管理負担が軽減する
従来のネットワーク管理では、拠点ごとに異なるルールや機器が存在し、それぞれの環境に合わせて個別に対応する必要がありました。担当者が現場に出向いて設定や確認を行うことも多く、運用の手間が大きな課題となっていたはずです。
しかし、新たな仕組みでは、アクセスの制御や監視が一元化され、場所に左右されずに状況を把握できる体制が整います。ポリシーを全社的に適用することで、拠点ごとのばらつきや手作業の設定ミスを抑えられます。
また、端末の状態や通信の履歴を自動的に記録する仕組みを活用すれば、日常の監視やレポート作成の負担も大きく削減されます。
さらに、異常な動きがあった際にはアラートで即時対応が可能なことから、問題発生時の初動も迅速になります。管理者にとっては、広範な環境を一元的に見渡せるという点が、実務上の大きな効率化につながるのです。
ゼロトラスト導入時の注意点

仕組みとしての堅牢さが注目される一方で、導入にあたっては事前に知っておくべき課題も存在します。現場への影響や既存環境との調整を怠れば、思わぬトラブルを招く可能性もあります。ここでは、検討段階で把握しておくべき代表的なリスクと、それに向き合う視点を紹介します。
システム統合や初期設計に手間とコストがかかる
新しいモデルを導入する際、多くの企業が直面するのが「どこから手をつけるべきか」という課題です。既存のネットワーク構成、アプリケーションの認証方式、従業員の業務プロセスなど、さまざまな要素を整理したうえで全体像を描く必要があります。
また、ユーザー管理やデバイスの可視化といった基本機能を実現するには、複数のツールを連携させる必要があり、その設定や検証には一定の時間と労力が求められます。特に拠点ごとに異なる環境が混在している場合、統一ルールを適用するには調整が欠かせません。
さらに、クラウド・オンプレミス混在環境への対応や、システム間のデータ連携なども考慮する必要があります。導入前の設計段階での見通しが甘いと、実装後に想定外の不整合が起きることもあり、事前準備に十分な時間とリソースを確保することが求められます。
ユーザー体験が低下しやすい
堅固な管理体制を構築する一方で、利用者にとっての利便性が損なわれてしまうケースもあります。たとえば、多段階認証の導入によりログイン操作が煩雑になったり、アクセス制御が厳しくなり過ぎたことで必要な情報にすぐたどりつけなくなるといった事例が挙げられます。
こうした状況が続くと、「使いにくい」「融通が利かない」といった不満が広がり、結果として現場での非公式な回避行動(シャドーIT)を誘発する危険もあります。
仕組みの導入とあわせて、ユーザーの理解を得るうえで必要な説明や、業務内容に応じたルール設計が不可欠です。さらに、操作性を保ちながら対策を実現するには、認証方法の選択肢を柔軟に持たせる工夫や、画面遷移の最適化といったUXの観点も重要になります。利便性と防御力のバランスを取る設計が、運用の成否を左右します。
ツール選びや技術の理解が不十分だと脆弱性が生まれる
導入時には多くの選択肢があり、どの製品や構成を採用するかは非常に重要な判断となります。しかし、外部ベンダーの提案を鵜呑みにしたり、機能の一部だけを理解して導入を急ぐと、意図しない抜け穴を作ってしまうことがあります。
たとえば、ID管理の仕組みが社内の人事システムと連携できていないケースでは、退職者のアカウントが残り続けてしまう危険性があります。また、デバイスの認証に対応していないツールを用いた結果、私物端末からの不正な接続が検知できないまま業務が進行してしまうこともあります。
さらに、製品間の連携が不十分なまま構成された場合、各ツールが想定通りに機能せず、問題発生時に責任の所在が曖昧になることも考えられます。
技術そのものを正しく理解し、自社の業務や既存システムとの整合性を確認したうえで選定・設計を進めることが、見えにくいリスクを防ぐ上で不可欠です。
社内文化・業務プロセスとの衝突が起こることも
制度や仕組みが整備されたとしても、実際に使う現場の理解と協力がなければ長続きしません。特に、慣れ親しんだ業務フローや操作手順が制限されると、抵抗感が強まり、導入そのものが頓挫するケースもあります。
たとえば、これまで自由にアクセスできていたファイルサーバーが突然制限されたり、出張先からの接続方法が変更された場合、業務に支障が出ると感じる社員も少なくありません。こうした不満が蓄積されると、無断で私的な手段を使うようになり、本来防ぐはずだったリスクを逆に拡大させてしまう恐れがあります。
新しい体制を取り入れる際には、単にルールを押し付けるのではなく、対象となる部署やユーザーと丁寧に対話しながら、納得感のある導入を心がける必要があります。教育だけでなく、現場の声を設計に反映させる姿勢が、定着の鍵となります。
ゼロトラストを導入する際に必要な要素
信頼を前提としない新しい考え方を実現するには、それを支える複数の仕組みが必要になります。特定の技術や製品だけで完結するものではなく、複数の要素を組み合わせて全体像をつくり上げていくことが求められます。ここでは、特に基本となる機能と運用体制に絞って紹介していきます。
ID管理(IAM)とアクセス制御の整備を行う
誰が、どのシステムに、いつ・どこからアクセスできるのか。こうした情報を一元的に管理し、正しい権限を適切に割り振る際に不可欠なのがID管理の仕組みです。特に組織が大きくなるほど、アカウントの作成や削除、権限変更などの作業が煩雑になり、管理ミスがリスクにつながる場面が増えていきます。
ID管理の仕組みを導入することで、各ユーザーの属性や役職に応じた権限設定が行えるようになり、不要なアクセスを防ぐことが可能になります。また、アクセス状況のログを記録することで、不審な挙動の把握や後追いの検証にも役立ちます。
加えて、アクセスを許可する際には、IDだけでなく複数の要素を組み合わせた認証(多要素認証)が標準化されつつあります。これにより、なりすましの防止や、情報流出リスクの低減につながります。IDを起点とした統制の仕組みは、全体の信頼性を支える基盤となります。
デバイス認証・MDMなど端末のセキュリティを確保する
どれだけ厳格な認証を導入しても、その先にある端末が無防備では意味がありません。従業員が利用するパソコンやスマートフォンが、安全な状態に保たれていることを確認する仕組みが必要です。ここで重要になるのが、端末ごとの認証と、端末管理の自動化です。
まず、アクセスを許可する前に、登録済みの端末かどうかを判別する機能を導入することで、私物端末や不審な機器からの接続をブロックできます。さらに、モバイルデバイス管理(MDM)を活用すれば、OSのバージョンやセキュリティパッチの適用状況を一元管理でき、不正な状態の端末は自動的に接続を拒否する運用も可能です。
また、万が一紛失や盗難が発生した場合にも、遠隔からのロックやデータ削除といった対処が取れることから、被害の拡大を防ぐことができます。こうした仕組みは、テレワークや外出先での業務が増える現代において、現実的かつ必須の対策といえます。
通信の暗号化・ネットワークセグメンテーション
情報のやり取りが社内外にまたがる今、通信の内容が第三者に傍受されるリスクを最小限に抑えるには、暗号化が不可欠です。メール、ファイル共有、業務アプリケーションを問わず、すべての経路において通信内容を見えない状態に保つことで、途中で情報が抜き取られても内容が判読されることはありません。
また、社内ネットワークをひとつの空間として扱うのではなく、役割や機能に応じて小さな単位に分割するネットワークセグメンテーションも重要な考え方です。たとえば、経理部門と開発部門、製造ラインと事務エリアが同じネットワーク内にある状態では、一か所の侵入で全体に影響が及ぶ恐れがあります。
そこで、アクセス範囲を最小限に絞り、必要な通信だけを通す仕組みによって、万が一の侵害時にも被害の拡大を防ぐことが可能です。外部との通信だけでなく、内部の移動にも制御を加えることで、全体としての堅牢性が向上します。
アクティビティの可視化とログ管理
誰がどの情報にアクセスしたのか、いつ・どこから接続したのかといった行動履歴を把握できる体制は、トラブルを未然に防ぐうえでも、発生後の原因追及においても極めて重要です。
可視化とは、こうした操作や通信の状況をリアルタイム、もしくは近い形で把握し、異常な動きがあれば即座に把握できる仕組みを指します。たとえば、深夜帯の大量アクセスや、拠点をまたいだ短時間でのログイン試行などは、早期に検知すべきサインです。
一方で、ログ管理はその記録を継続的に保存し、必要に応じて分析や監査ができるようにしておくことを意味します。これにより、インシデント発生時の調査はもちろん、運用ルールが守られているかの定期的な確認も行えるようになります。
まとめ
社内外の境界があいまいになった現代において、従来の防御モデルでは限界が見え始めています。そこで注目されるのが、あらゆるアクセスに対して検証を行い、必要最小限の操作だけを許可するという考え方です。
この仕組みを導入することで、テレワークやクラウドサービスの活用が進む環境でも、拠点ごとのばらつきを抑えた統一的な運用が可能になります。一方で、設計や導入には手間がかかり、既存の業務や文化との衝突も生じやすいことから、段階的な取り組みと全社的な理解が欠かせません。
技術と体制の両面から備えることで、変化の多い時代にも対応できる柔軟な防御基盤が築かれます。本記事を通じて、自社に必要な対策の方向性を見つける一助となれば幸いです。